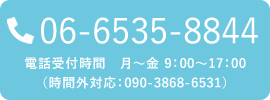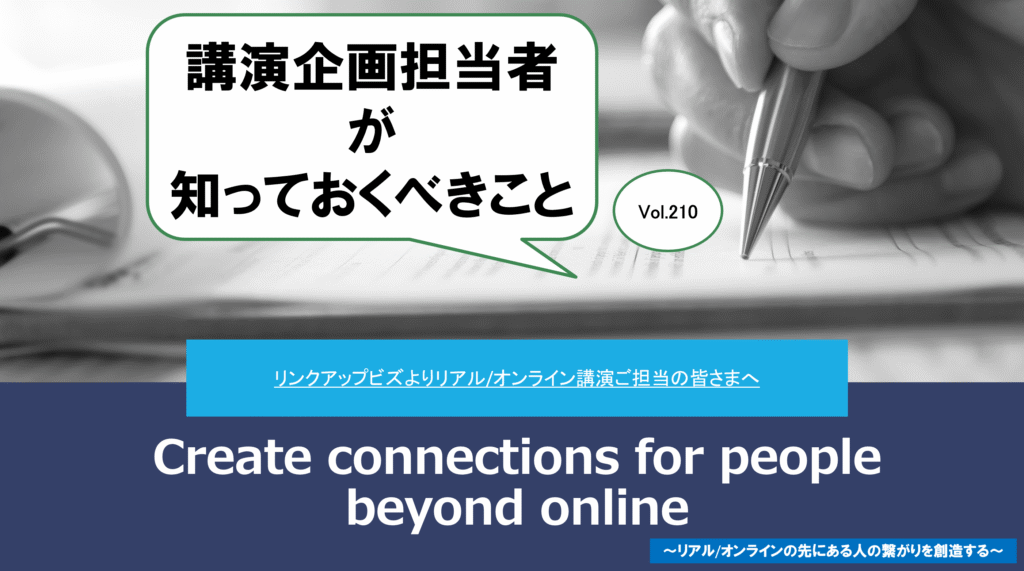
–ヒューマンエラーの予防と対策–
人を理解することが最初の一歩。人はなぜ間違える?どう防ぎますか?
・・・「ヒューマンエラー」といっても“うっかりミス”から“損失を出すミス”や“命に関わるミス”まで様々です。人が誤認識・誤動作によって引き起こしてしまう「ヒューマンエラー」は、多大な損失を招く恐れがあり、そのようなリスクを回避するため、多くの企業が対策を講じています。

エラーを減らし、取り返しのつかない損失を減らし、企業の風土改善を図るための「ヒューマンエラー講演会」・・・人間が「なぜミスを犯すのか」「なぜミスに気づけないのか」といった観点について心理学の立場から探ります。
「人間は、エラーを起こしやすいもの、ゆえに常に安全について工夫し、考え続ける姿勢が必要」なのです。


『安全行動力向上研修 〜ヒューマンエラーを防ぐ習慣づくり〜』(平貞隆史さん)
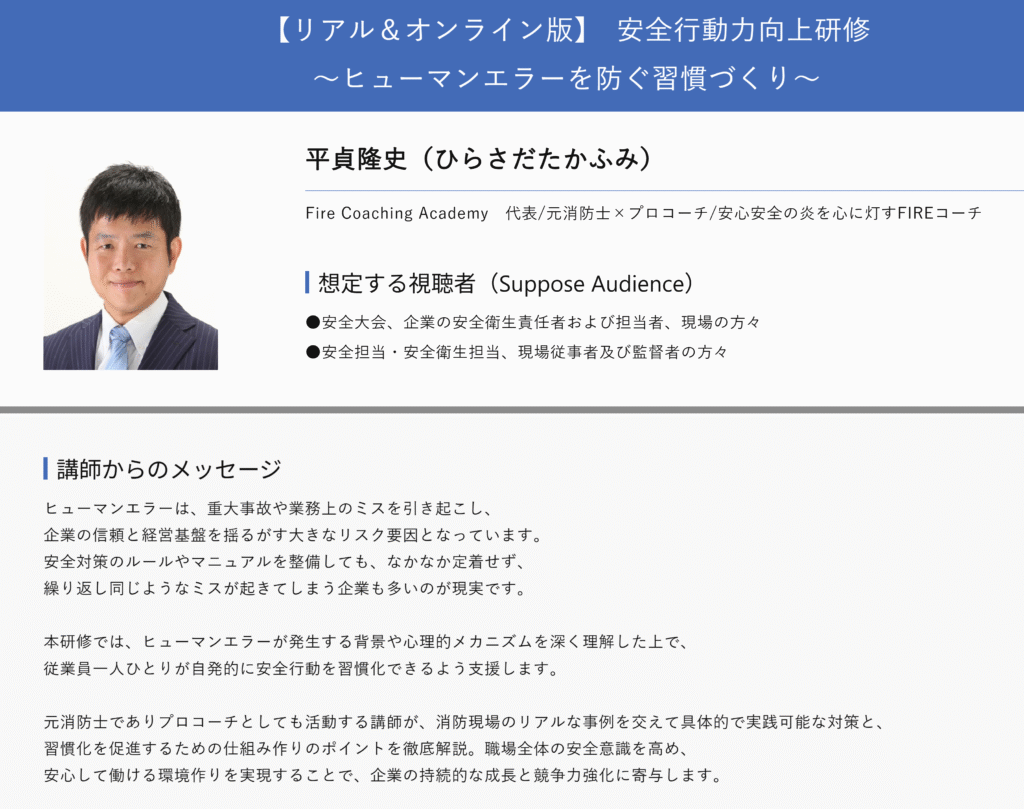
・訓練には意味がある”ということが、消防の現場事例を通して実感できました。単なる避難訓練ではなく、“チーム力”や“人材育成”にもつながり、平常時の経営にも効果がある』という視点は新鮮でした。
・『ヒヤリハット』の事例紹介がリアルで、他人事では済まされない内容でした。特に、高所作業や機械使用に関するリスク対策や安全対策の“3つのポイント”は、シンプルで実践しやすく今日から現場で取り組みます。
・BCP対策が平時の経営改善になることを知り、従業員とお客様の安全を守る責任を改めて感じました。

『重大災害の芽となる 〜ヒューマンエラーの防止対策〜』(富田 勉さん)
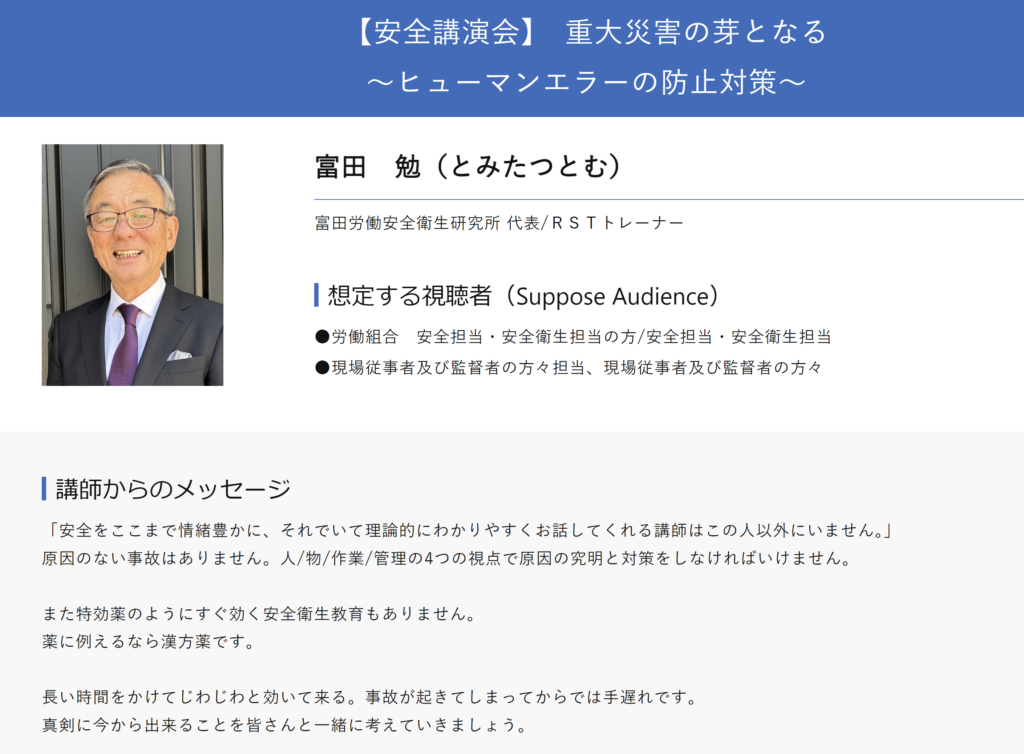
・今回の講演会は、安全に対する意識を高めるため現場作業員を中心に参加いただいた。講師の富田様の講演は、ご自分の経験も踏まえたうえでお話しいただけたので、出席していた現場作業員へ伝わりやすく、発見も多かったと思います。
・当初の計画より、現場作業員、監督者、管理職など多くの方に出席いただくことができました。今後、講演会で得た知識や発見をどう活かすかにもよりますが、集中して講演会に参加してもらい、まずは成功と考えています。
・話が聞きやすく、参加者へ問いかけるなど、飽きないよう工夫されており、非常に参加しやすい講演会でした。また、ご自分の経験を踏まえた話も多く取り入れていただき、同じ製造業として理解しやすかった。

『エラーマネジメント実践セミナー 〜エラーの連鎖を切る2つの方法〜』(清水孝久さん)

・管理者層の受講者に対して、部下とのコミュニケーションが重要であるというところは十分伝わったと思います。些細なエラーやルール違反が大きな事故に結びついてしまうことが良くわかった。
・クイズ等でエラーを体感したり、一方的に話を聞くだけの内容ではなかったので、楽しく興味深く聞くことができた。
・エラーやルール違反に対する航空業界の取り組みの概要を理解し、具体的なヒントを1つでも職場に持ち帰り実践してもらうことが研修の狙いだったが、この点は達成できたと言われました。それと、毎年同じようにグループ会社を管理職を集めて研修を実施するが、2~3割の人は寝てしまうが、今回は寝る人は一人もいなっかったので驚いたとも仰っていました。

『ヒューマンエラー、こうすればなくなる 〜つもりではなくしっかり気をつける〜』(長谷川孝幸さん)
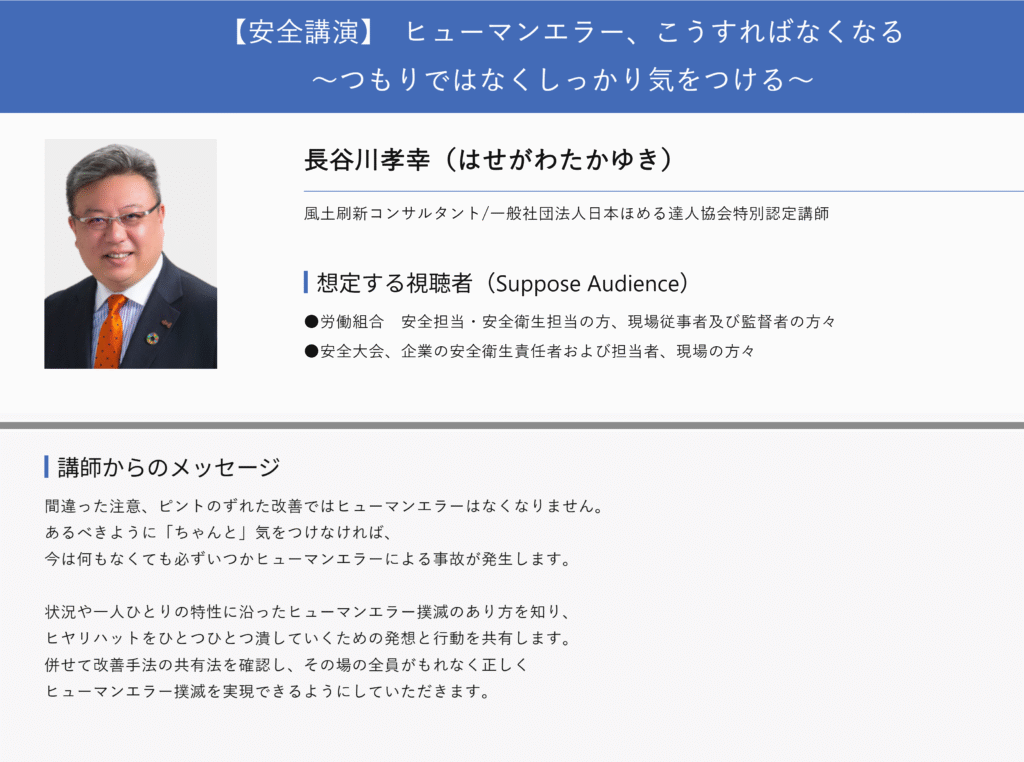
・安全大会や安全講習は義務だから受けていたが、内容には飽きていた。今回は楽しく受講することができよかった。
・製造現場だけでなく内勤職にも必要な考え方だと思いました。
・グループ会社の人たちにも聞かせたい。現業の人たちにもわかりやすいと思う。

『不安全行動/ヒューマンエラーと安全管理 〜危険感受性を高め危険敢行性を下げるには〜』(去来川敬治さん)
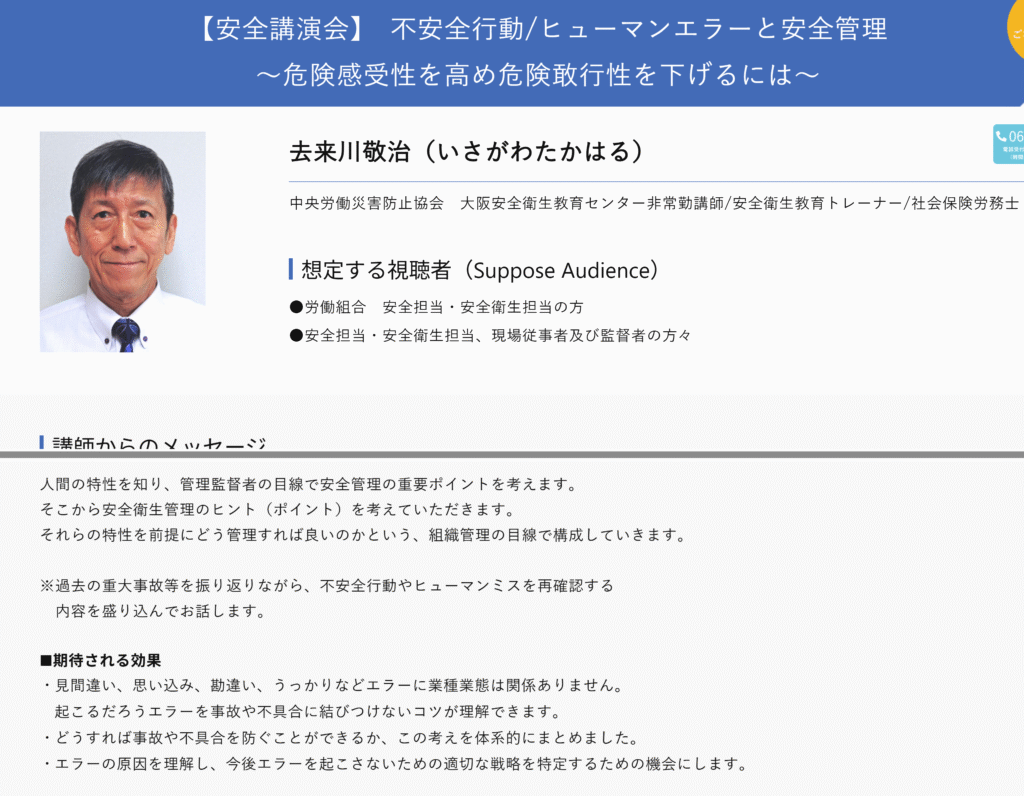
・人は忘れやすい動物であるという事を認めた上で、不安全行動を防ぐにはどうしたら良いかという事を考えさせられるものでした。感じさせ、理解・納得させるリーダーの一言、コミュニケーションはリスクを思い出させ、身構えさせる効果がある。
・受講者の職場環境に近い講演内容であったため、状況の想定が容易であった 会員への支援(サービス提供)に効果があった。会話・コミュニケーションのスキルが高く、受講者が講演に引き込まれていた。
・ほとんどの作業長、職場長に聞いてもらえました。不安全行動を防ぐ為には何に気を付けなければならないかを感じ取ってもらえたと考えています。

『安全行動をするための脳づくり 〜脳を創って安全を創る〜』(古橋麻美さん)
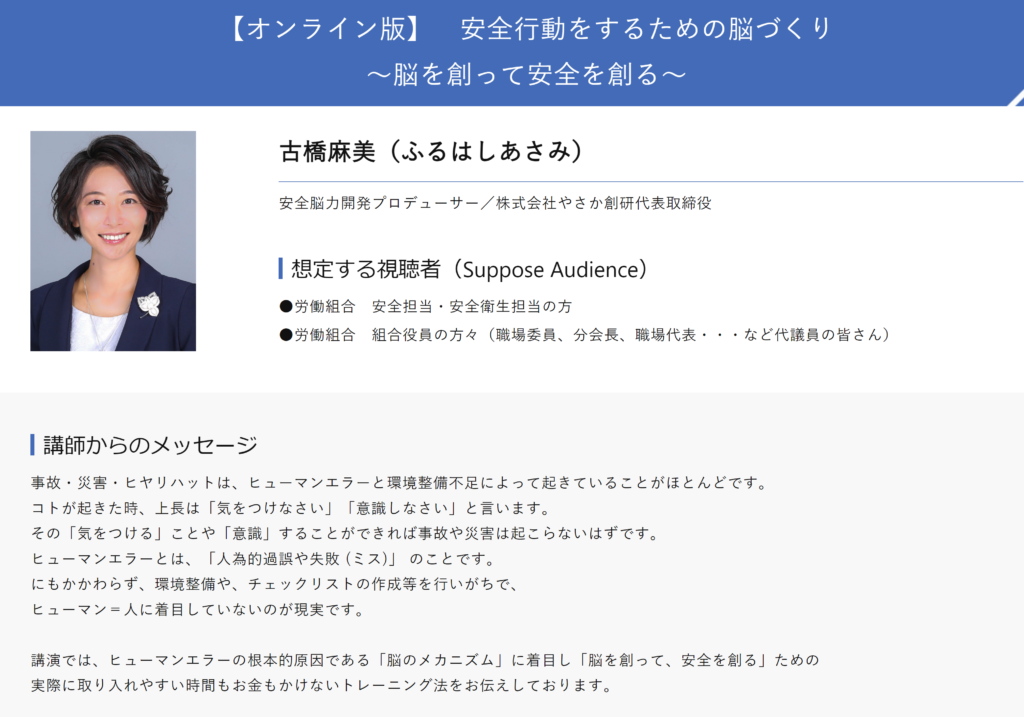
・今回の講習会は労働災害防止対策をテーマに開催しており、意識啓発としては概ねお目的は達成したものと考える。
・脳トレーニングは普段から職場で実践されることにより効果が図れるので、本当に効果が表れるのは受講生次第と考える。
・講義終了後も熱心に質問をしている方もおり、仕事の効率化を図ることの重要性を受講者は認識を更に高めたと思う。受講者を話しに引き込むのが上手い。参加型で飽きさせない。
・・・いかがでしょうか?リアル/オンライン講演事業に取り組まれる執行部さんのご参考になれば、幸いです。