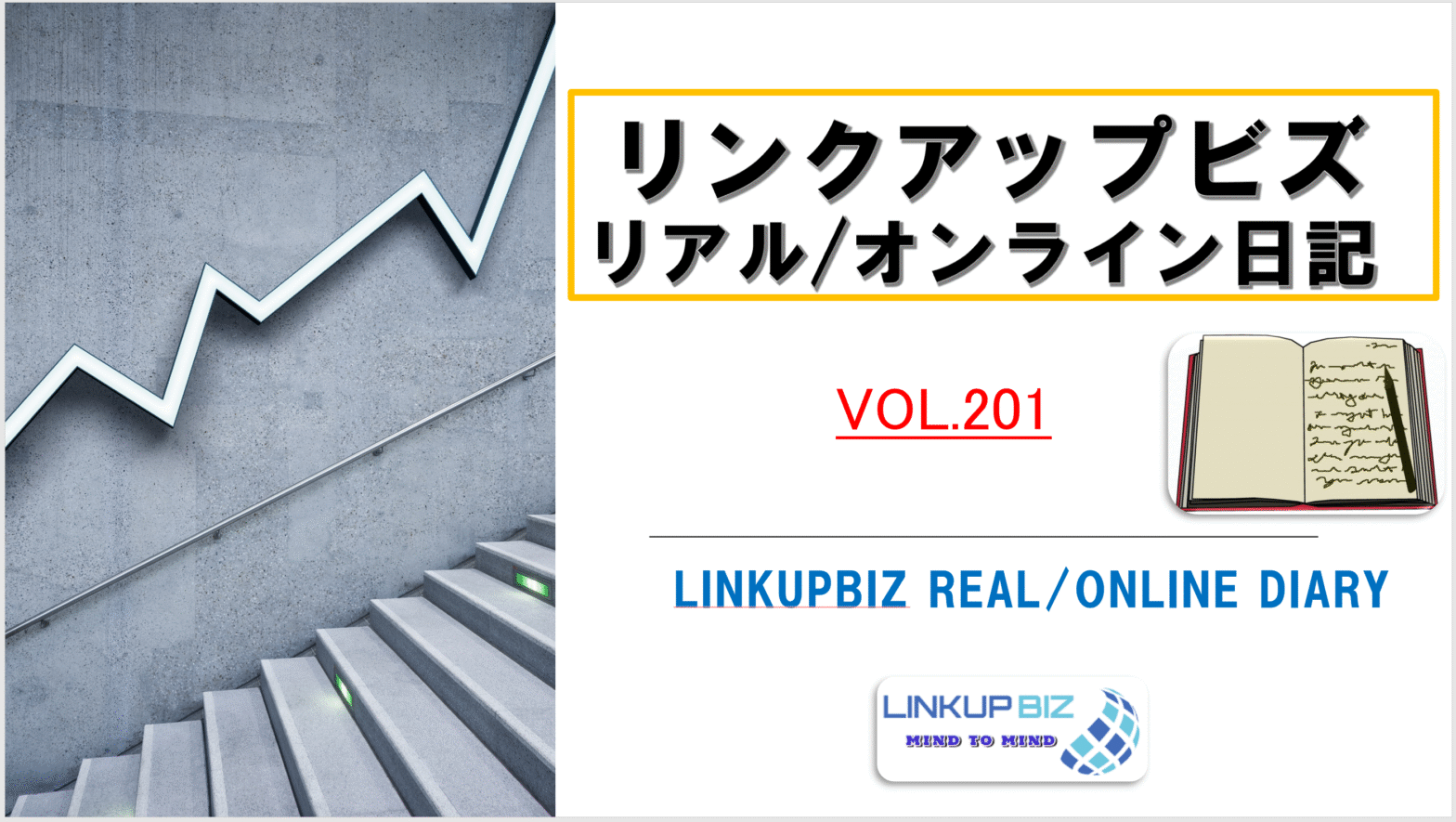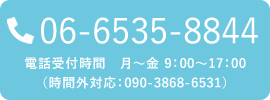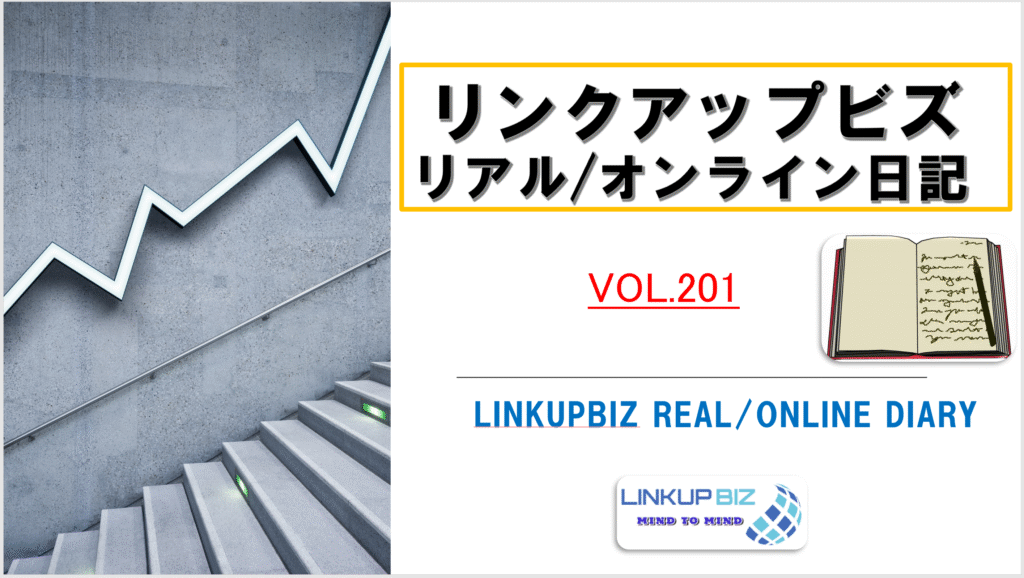
-持続可能な地域経済を目指す取り組み-
近年、災害やコロナ禍の影響などがあいまって、資金繰りに苦しむ地方企業は少なくありません。地域金融機関では、このような企業に対して、事業再生サポートへの取り組みを強化しています。
IT化の著しい現代においても、都市圏から距離のあるローカルエリアではやはり、ビジネスが進めにくい側面があるでしょうし、人口減少や高齢化などにより産業が弱体化する動きも各所にみられます。

安定した雇用なくして、地域経済は成り立ちません。こうした状況に、地方銀行による企業の事業再生支援への積極的な取り組みが目立つようになりました。その背景には、地域経済の活性化だけでなく信用リスク低減や手数料収入アップなどといった狙いもあるようです。
-銀行取引先/経営者の会-
上記のような背景も含め、各地方銀行さんでは会員企業経営者の勉強会(情報交流会)を開催されており今回、豊岡厚惠さんをお招きして、事業後継者の勉強会を目的に講演会を開催されました。
経営者/経営幹部の方々の情報源、研鑽と交流の場を提供させていただきます。

主に下記項目を伝える内容となっております。
・社員がヤル気になって主体的に動くようになる秘訣
・社員との信頼関係を築く3ステップコミュニケーション術
・明日からすぐできる実践ポイント
・部下が動き出すコミュニケーション術とは
-社員がやる気になって主体的に動くようになるには-
上司/リーダー側は「言われた事しかしない 指示待ち」「こちらの出す指示の意図が伝わらない」と思っていますが、部下側は「上司の思うようにしないと“なぜこんなやり方をする”と言う」「指示だけ出すけど、なぜ、どうしてするか、目的を教えてくれない」etc.、上司と部下の間には結構なギャップが生じているのが実情です。

指示待ち人材は何故できるでしょうか? ・・・時間がないからと、具体的なやり方を指示してこちらの言った通りに行動させようとするから、部下が自分で考え、自分で判断することができなくなり、結果自分から意見を言わなくなり、いつも指示が出るのを待っているだけなってしまう・・・
こういうご経験、身に覚えがありませんか?我々は知らず知らずのうちに、指示待ち人間を育成していたのかも知れません。
-コミュニケーションの量が減ることで起きる弊害-
職場でのコミュニケーション不足は様々な弊害を起こす可能性があり、上司が部下のスキルと意欲の把握ができなくなることで、正しい評価ができず部下はモチベーションダウンし、最悪離職の可能性も出てきます。

上司の指示を受けてから必要最低限のことしかやろうとしない部下は、自分で考えることをせず、上司に依存している状態と言えますが、これは部下だけの問題ではなく、上司が部下の意見を「傾聴」していない場合が多いのです。聞いたとしても、自分の意見が正しいという前提を変えることはほとんどしなかったり・・・
そのような状況では、部下は「どうせ決めるのは上司なのだから」と自分で考えたり動いたりしなくなり、指示待ち人間になってしまい、結果業務においても致命的な問題となりうるのです。

「誤解が生じる」「壁ができる」「ミスやトラブルが発生しやすくなる」など、コミュニケーションが不足することで生まれる感情は結構あり、コミュニケーションが不足することによる障害としては、「迅速な情報共有に支障 こまめな報連相を怠る」「部門、事業所間の連携が取りづらい」「サービスの質が低下 、顧客に影響を及ぼす」といったことになります。
-部下がヤル気になって主体的に動くようになる秘訣-
関係の質を高める&「信頼関係」の構築・・・これが土台で、ここがないと先に進めません。
ビジネスを取り巻く状況の変化が速い今は、有能な上司が過去の経験をもとに方針を決めても、現状にそぐわないということは頻繁に起きている一方で、現場や顧客に近い部下のほうが、ニーズや市場の変化に早く気付くこともあります。
上司が部下の持っている最新の情報を吸い上げ、それを判断材料に加えれば、環境の変化により適応した決断を下せるのです。
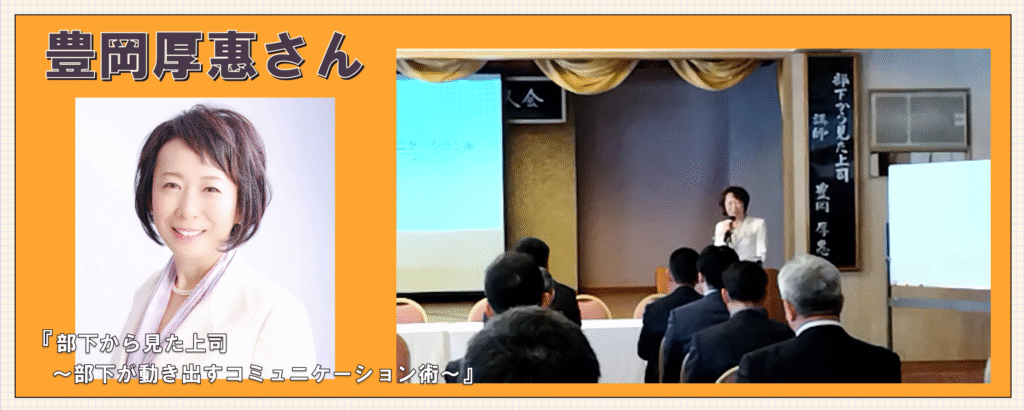
そのためには部下とのコミュニケーションの質を高めることが必要で、相手の意見も取り入れ、自分の考えを更新することが望ましいです。「自分一人でも正しい判断ができる」「部下にいわれて意見を変えるのは、上司としての威厳が損なわれる」といった考えを捨て、部下の意見を取り入れる柔軟性を示す時代になっています。
どれほど優れた経営者でも完璧な未来予想や判断は不可能なのだから、コミュニケーションの結果、考えを変えることは決して悪いことではなくむしろ、より現状に即した形となり、話し合った効果が生まれます。最終的な決定が部下の意見と異なっていても意見を聞いてもらえたことで、部下のモチベーションにもよい影響を与えるのです。
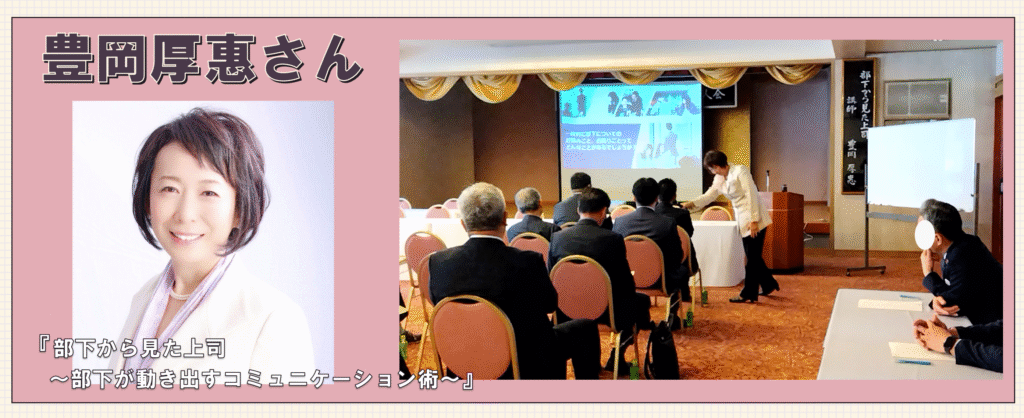
・・・言われたことしかやってくれない、どうみてもヤル気がなさそうだ、叱るとすぐにふくれる、自分がやったほうが早い、大切な仕事は任せられない等、期待とは裏腹に思うように動いてくれない部下。
そんな時に今するべきことは何か?部下がやりがいを持ち生き生き仕事に取り組んでもらうには?長年従業員さんの指導に携わってきた経験から、部下がみるみる変わる秘訣が大好評の講演です。

『部下から見た上司 〜部下が動き出すコミュニケーション術〜』(豊岡厚惠さん)
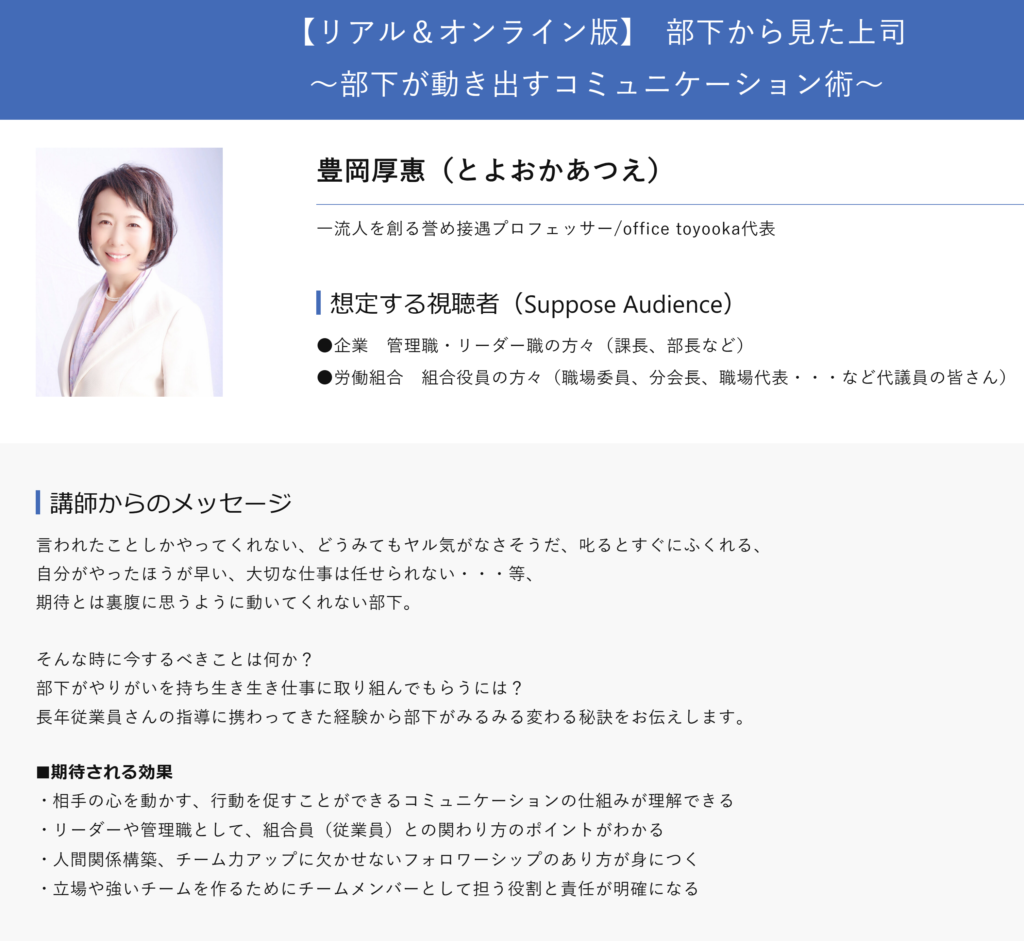

・良かったです。当たり前の内容だけで出来ていなかったな、という声も多かった。非常に好評でした。
・上司と部下ということで、互いのギャップが大きくあることに驚きましたし、経営者/上司としてとても参考になる内容でした。
・「部下が動き出すコミュニケーション術」ということで、話を伺うと「良い」とは分かっていても出来ていないことが多く、反省するきっかけになりました。
・上司として、今までの行動や言動を見つめ直し、これからの仕事に活かせ、リーダーとして向上して行けるよう努めていきたいと思いました。

・その人の「重要感」を満たすことにより、幸福な気分になっていただく=自分の幸福につながるものと認識し、今後もいっそう「目配り・気配り」をできる範囲で行なおうと思いました。他者がいて磨かれていくと思うので、これから出会う人の「縁」を大事にして必ず、信頼関係を築いていけたらと、思います。
・たくさんの学びをありがとうございました!基本から深いところまで学ばせていただくことができました。
・まだ足りないとこも多いですが、この学びをしっかりと身につけ、自然に行動できるように実践していきたいです。
・常に学ぶ気持ちを持つことで、自分自身をさらに高めて行くことが出来るということを学ぶことが出来、充実した講義でした。