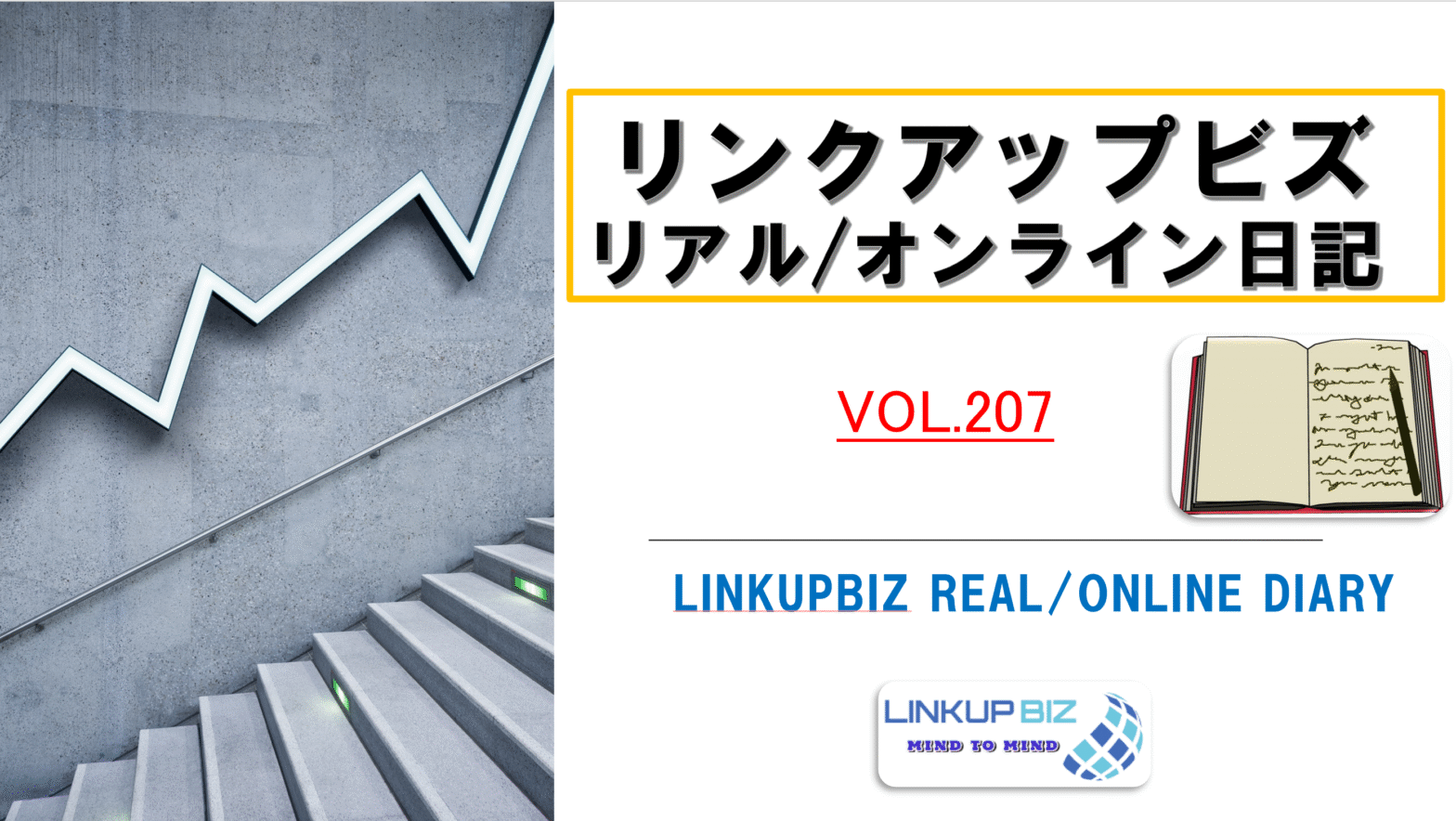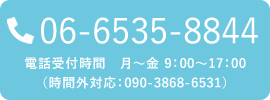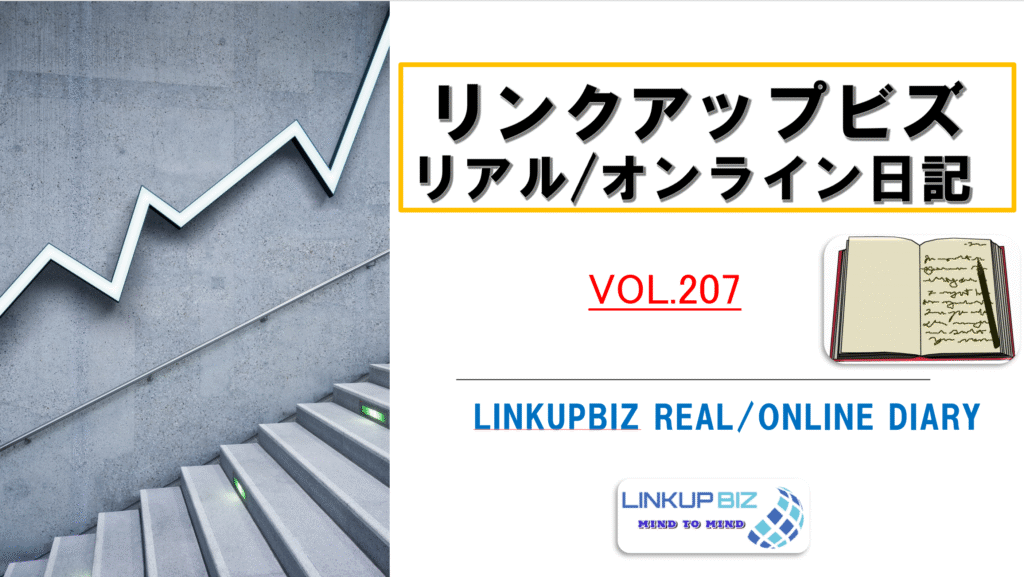
-やらされ感の正体とその組織への影響-
「やらされていること」と「行っていること」が同じことでも、本人の気持ちには大きな違いがあります。
「なぜこんな仕事をしなければならないんだろう…」「言われたからやっているだけ…」・・・こんな思いを抱えながら仕事をしている社員/従業員はいませんか?
これこそが「やらされ感」の正体です。

いい時間を過ごすための秘訣は、1.楽しむことから始める 2.笑顔、うなずく、拍手 3.自由な発想で取り組む こと。
ちなみに「エンジョイ」することでもたらす効果としては、あるアメリカの大学の研究した笑顔の経済効果は280万円だと言われております。
-職場で活かすモチベーション-
本人のやりたい気持ちを一切無視した、仕方なく嫌がりながらやっているということです。 自分がいやいや感じているところに成長はありません。
やらされ感とは、自分の意思や価値観とは無関係に、外部からの指示や義務感だけで行動している状態のこと。 この「やらされ感」が蔓延すると、組織にはさまざまな悪影響が出てきます。
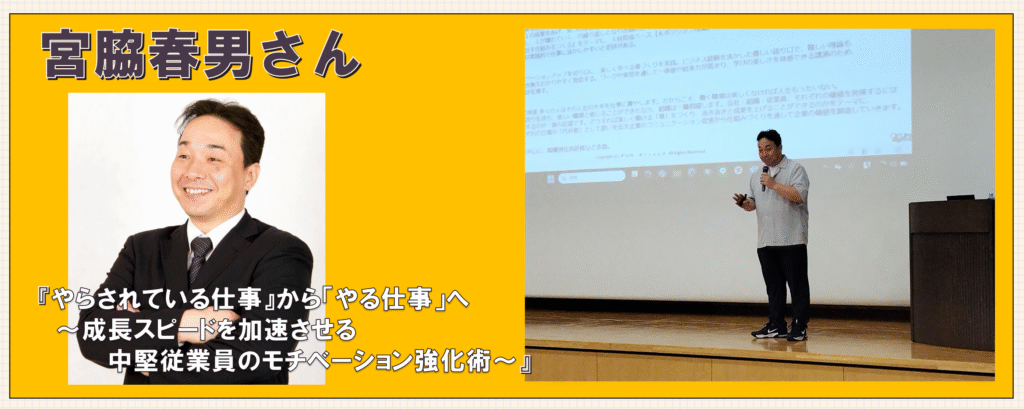
そこで職場が整える「エンゲージメント」を高める支援が大事になってきます。
1.働きやすい環境の整備
2.成長とキャリア形成の支援
3.従業員を大切にする企業文化
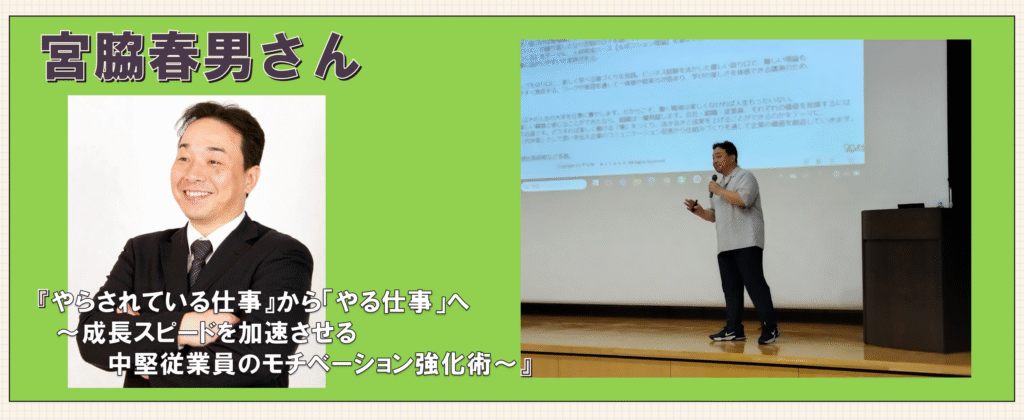
・・・やらされ感満載だと、まず目に見えるのは生産性の低下。 自分ごと化できていない仕事は最低限のことしかやらなくなり、創意工夫や改善提案も生まれにくくなります。 さらに深刻なのは、この状態が長く続くと社員のメンタルヘルスにも影響し、離職率の上昇にもつながることです。
これからの時代、単なる指示待ち人間ではなく、自ら考え行動できる人材こそが企業の競争力を高める鍵となるのです。
-中堅社員5年目のジンクス-
社会人3年目ぐらいから、多くのビジネスパーソンが新人の枠を超え、より大きな責任と期待を背負うようになります。 この時期、手取り足取りの指導が減り、一人前として独立した業務遂行が求められるようになります。
厚生労働省が発表したデータによると、入社3年以内の離職率は30%を超え、この時期の挑戦がいかに大きな壁となるかを物語っています。
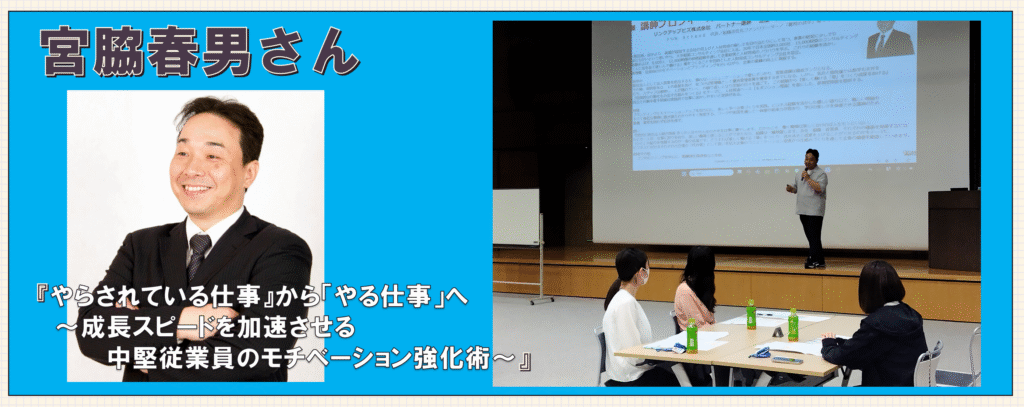
5年目のジンクスとしては、1.キャリアの不安 2.評価の不満 3.後輩、部下との関係 4.ワークライフバランス だと言われています。
仕事とプライベートのバランスを保ちながら、趣味やリラクゼーションを通じてメンタルヘルスを維持することも、焦らずに仕事を進める上で重要な要素です。 自分自身のペースを見失わず、持続可能な働き方を模索することが、5年目のジンクスを乗り越える鍵となります。
-自律型人財がもたらすパフォーマンスの違い-
従業員一人ひとりの「モチベーション」が上がれば、仕事効率も上がり、職場も活性化し、業績も上がります。 しかし価値観が多様化した昨今、表面的かつ対処療法的な手法では、従業員のヤル気を引き出すことは困難です。
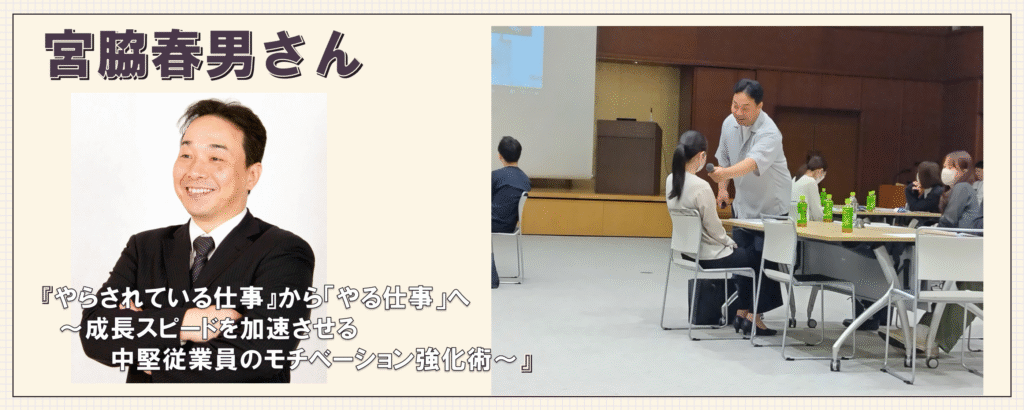
究極のモチベーションは「愛の力」です。人を結び付け、素晴らしい人間関係の輪をたくさんつくっていきましょう。その上で、あなたが人を好きになる人から好かれる対人関係能力を高めていくことが必要になります。
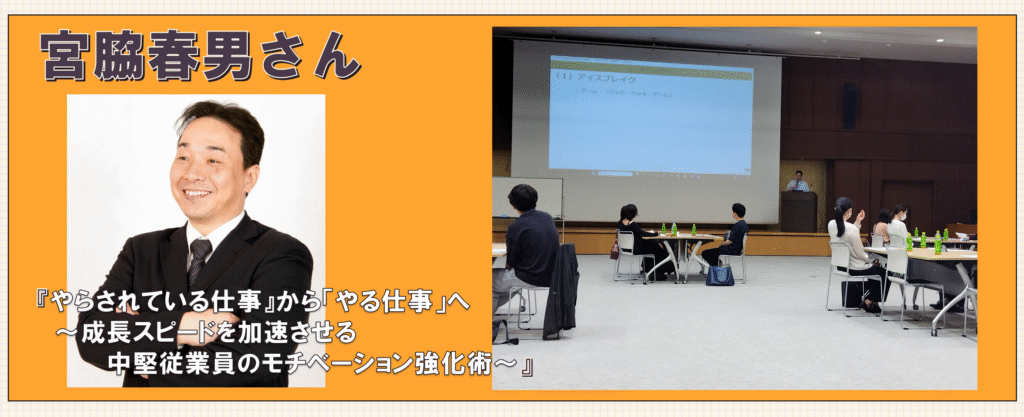
やるべきことを明確にし、意味を持って具体的な行動に移せるようになり、 参画型のワークや実習を通して、楽しみながら自発的に体得できます。その上で若手/中堅組合員の成すべきことを再認識していただき、職場においても、組合活動においても活用できるポイントを自身のものにしてください。

『「やらされている仕事」から「やる仕事」へ 〜成長スピードを加速させる 中堅従業員のモチベーション強化術〜』(宮脇春男さん)
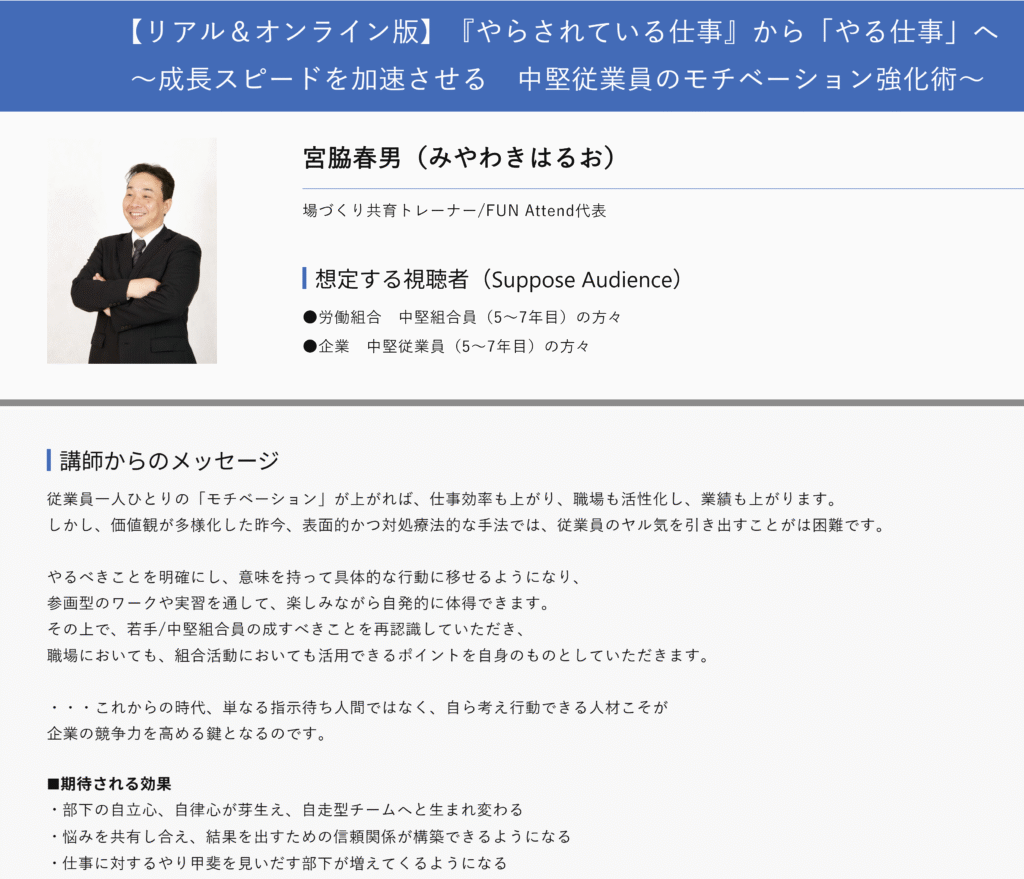

・良かった!です。良い意味で楽しい内容で、タメにもなる内容でした。
・同期が集まる会だったので、グループワークが入ってましたが色々話しやすかったです。
・とても参考になる内容でした。仲々自発的に動くのが苦手でしたが、そのきっかけになる時間だったと思います。グループワークもあり、飽きずにアッという間の時間でした。
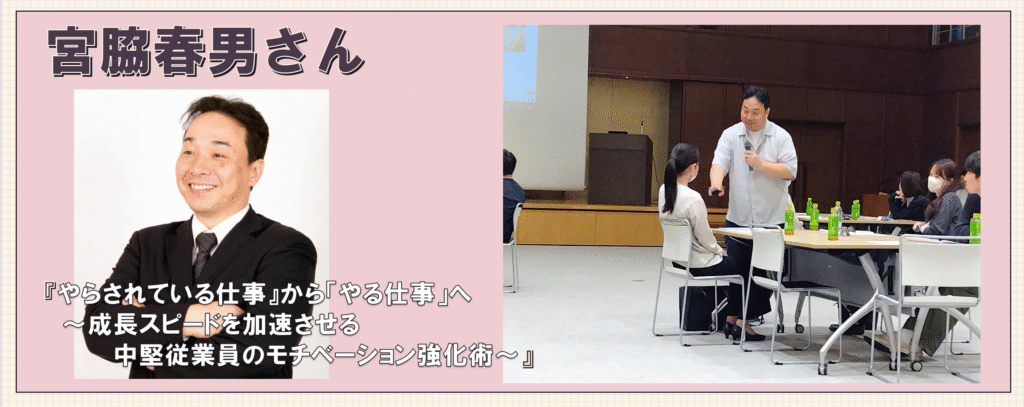
・講義形式と違い深く話を聞くことができました。ひとりに向き合うって、会社においても同様に必要なことですね。
・今日の話を聞いて、明日から自ら率先して色々動いていこう!という前向きな気持ちになりました。参加して良かったです。ありがとうございました。
・おとなしくあまり表現しなかった社員が自ら手をあげて発言するなど積極的に行動するようになった。お陰で周りのスタッフに良い影響がでました。
・これだけ全社員で楽しく話ができたのは初めて。仕事上コミュニケーションはとれていると思っていましたが、現状の業務連絡がほとんどでした。これからの会社の方向性やあるべき姿を話し合えたことで、会社が一つにまとまった気がします。