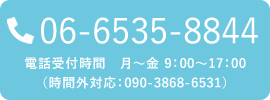〜自己肯定感の低い子に親ができること〜


-
平岩国泰(ひらいわくにやす)放課後NPOアフタースクール代表理事
想定する視聴者(Suppose Audience)
●労働組合 全階層の方々(若手組合員から組合役員まで)
●教育・福祉・子育て支援に関わる行政・NPO・企業の方
●子育てに悩みや迷いを感じている保護者の方々
●保育・教育現場で子どもと関わる先生方
内容
- 01
-
自己肯定感とは何か
・「失敗しても自分は大丈夫」と思える感覚が自己肯定感の土台
・自己肯定感が育っている子は、挑戦を恐れず、他人の評価に振り回されにくい
・親の言葉かけや態度が、日々の積み重ねとして自己肯定感を育てる
- 02
-
子どもが伸びる「褒め方」のポイント
・結果よりもプロセスを褒める:「がんばったね」「工夫したね」など
・存在そのものを認める:「いてくれて嬉しい」「あなたが大切」
・過去の自分との比較を使う:「前よりできるようになったね」
・子どもの意思決定を尊重する:「自分で選んだんだね、すごいね」
- 03
-
折れない「叱り方」の工夫
・感情的に叱らず、行動に焦点を当てる:「〇〇したことは困るけど、あなたのことは大好き」
・感情的に叱らず、行動に焦点を当てる:「〇〇したことは困るけど、あなたのことは大好き」
・叱った後にフォローする:「どうすればよかったと思う?」と一緒に考える
・ 叱る=否定ではなく、成長の機会として伝える
- 04
-
放課後の現場から見えた子どもの変化
・「褒められすぎてやる気を失う子」もいる
・“褒める”は万能ではなく、子どもに合った関わりが必要
・ 放課後の自由な時間にこそ、子どもは自分を試し、自己肯定感を育てている
担当者より
叱ることが怖い」「褒めても響かない」――子育ての中で誰もが悩む“声かけ”の方法。
でも、ちょっとした言葉の選び方で、子どもの心は大きく変わります。
子どもの「やってみたい」を引き出すヒントが、きっと見つかります。
放課後NPOアフタースクール代表理事・平岩国泰さんが、5万人以上の子どもと関わってきた経験をもとに、
自己肯定感の低い子どもにこそ届く褒め方・叱り方を、実例とともにわかりやすく解説します。
●講演実績
某精密機器メーカー労組、某企業グループ 社内セミナー、ベネッセウェルビーイングLab 共催フォーラムなど
●オンライン講演記事
【講演テーマ一覧】
1.現代を生きる子供のために 親ができること ー安全基地で子供は伸びる
2.子供が伸びる褒め方・叱り方 ~自己肯定感の低い子に親ができること~
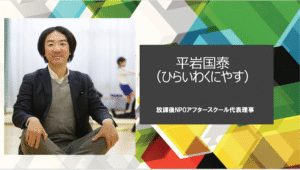
3.地域で子どもを育てる ~アフタースクールの挑戦~
※平岩国泰さん印刷用プロフィール資料
(制作:リンクアップビズ)
(視聴者ご感想)
・たくさんの子どもたちと真剣に向き合ってきたからこその、具体的な考え方、
関わり方なのでとても理解しやすい内容で、きっと子育てが楽になります。
・ついつい子どもを他の子と比べてしまったり、できることできないことに目がいってしまって
成果ばかりみてしまったりします。その子の中の育ちや道しるべを一緒に感じ一緒に楽しんでいきたいと思いました。
・『ほめるより気付く』・・・今日1日の景色が少し変わりました。
・私自身、子供が自己肯定感をもって自信をもって生きていってくれることが一番大事だと思っており、
講演ではその思いをさらに強めてくれました。また実際に子供にかけるべき言葉を、
実例で示してくれるため、実際の育児にも役立てることができると感じました。
・参加者からは「子どもとの関わり方を見直すきっかけになった」
「親としての安心感が子どもに伝わることの大切さを実感した」といった声が多く寄せられています。
・「子どもにとっての“安全基地”」という言葉が心に残りました。
親が安心感を与える存在であることが、子どもの挑戦する力につながるという話に納得しました。
・講演を聞いて、つい口出ししてしまう自分を反省しました。
子どもを信じて見守ることの大切さを学び、「待つ勇気」を持ちたいと思います。
・非認知能力の重要性を初めて知り、就学前に育てたい力として、
自己肯定感や感情のコントロールが紹介され、学力だけではない視点に気づかされた。
・放課後の時間が子どもの成長にとっていかに貴重かを実感した。
地域や市民先生との関わりが子どもに多様な経験をもたらすという話に感銘を受けた。
・講演後、子どもとの会話が変わった気がします。
「今日はどんな気持ちだった?」と感情に寄り添う質問をするようになりました。
・参加者からは「地域と子どもをつなぐ視点にハッとさせられた」「自分にもできることがあると感じた」
といった前向きな感想が多く寄せられています。
・子どもたちの抱える問題の深刻さや実態を詳しく理解できたし、データや現場の声を交えた話により、
放課後の孤立や居場所の不足といった課題がリアルに伝わり、好評でした。
・社会の一員として何ができるかを考えるきっかけになり、地域や企業が子ども支援にどう関われるか、
具体的なアクションのヒントを得ることが出来ました。
・“1校に1つのアフタースクール”というビジョンに共感した。
・地域の大人が子どもと関わる仕組みづくりに希望を感じた。
・企業としての社会貢献のあり方を見直す機会になった。
CSRや地域連携の観点から、子ども支援が企業活動とどう結びつくかを考える契機になった。